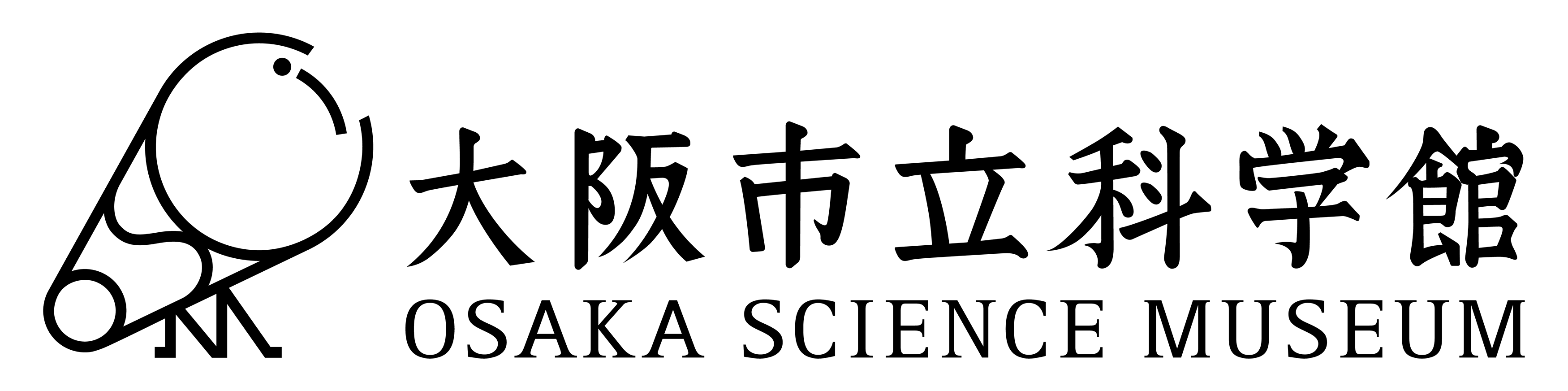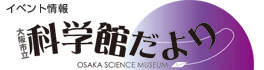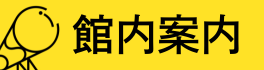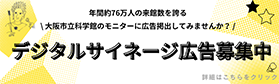プレスリリース
東洋初のロボット「学天則(がくてんそく)」の復元作業が終了 ー4月24日(木)に報道関係者向け内見会を行いますー
大阪市立科学館では、80年前に大阪で作られた東洋初のロボット「学天則」の復元を行ってまいりましたが、このたび作業が終了し、平成20年4月24日(木)午後3時より報道関係者向けに内見会を行います。
復元された学天則は、高さ3.2mと巨大なもので、オリジナルと同様、腕が動き、表情が変化する動態です。平成20年7月18日(金)午後1時より展示リ ニューアルオープンの目玉として大阪市立科学館にて一般公開する予定です。大阪の生んだ独創的なロボットが、観覧者の心に科学への関心と好奇心を生み出すことを願っています。

図.復元された学天則
東洋初のロボット「学天則」
学天則は、大阪毎日新聞社の論説委員だった生物学者、西村(にしむら)眞(ま)琴(こと)が製作したロボットで、1928年に京都で開催された大礼記念博覧会に出品され、話題になりました。東洋初のロボットとされています。
そもそも「ロボット」という言葉は、1920年にチェコの作家カレル・チャペックが「R.U.R.」という戯曲の中で使った造語であり、欧米では機械的な ロボットが作られていきました。しかし、もともと生物学者であった西村が製作した学天則は、動力源に圧縮空気を用い、表情までもが変化するという、生き物 らしい動きを目指したロボットでした。名前の学天則は「天の法則に学ぶ」の意味です。 学天則はその後東京ほか各地の博覧会などを巡回し人気を博しましたが、ドイツに渡った後に行方不明になったとされています。オリジナルは存在していません。
学天則の復元
大阪市立科学館では、1992年に学天則の模型を製作しました。これは、オリジナルのオムニマックス短 編映画「大阪 The Dynamic City」の撮影用として使用するためです。このときの模型は、現在館内で展示していますが外観を模しただけのもので、大きさは実物の約2分の1、動作機 構もついておらず、顔つきも現代的なものとなっています。
今回の復元は、オリジナルと同じ大きさ、動作になるように、乏しい資料を元に学芸員が研究したうえで復元したものです。その結果全高が約3.2mと巨大な ものになり、オリジナルと同じく圧縮空気を用いて、目・まぶた・頬・口・首・両腕・胸が動き、インスピレーションを感じると左手に持った「霊感燈」が光る ことも再現することとなりました。動作はコンピュータで制御しておりますが、西村眞琴が用いた「ドラム式制御」がわかる動作模型も製作しています。

図.失われたオリジナルの学天則(昭和3年ごろ)
学天則にまつわる話
映画に登場
学天則は、映画にも登場しています。1988年に公開された「帝都物語」(荒俣宏原作、実相寺昭雄監督)で、西村真琴の操作で鬼を退治するロボットという役どころです。なお、このさい西村真琴を演じた俳優西村晃(水戸黄門役で有名)は、西村真琴の次男です。
天体の名称
学天則は天体の名称にもなっています。太陽のまわりを巡る小惑星9786 Gakutensoku がそうで、群馬県のアマチュア天文家、小林隆男氏が発見したものに、大阪市立科学館の学芸員が名称を提案し、国際的に使用されて います。小惑星Gakutensokuは、現在うお座からおひつじ座にあり、太陽と重なっています。
制作者 西村真琴
略歴は下記の通りです。このほか、生物学者でマリモの保護に尽力したり、中国の戦災孤児の保護や保母の育成にあたったりと多彩な活動を行いました。
| 1883年(明治16年) | 3月26日、長野県生まれ |
|---|---|
| 1908年(明治41年) | 広島高等師範学校 博物学科を卒業 |
| 1911年(明治44年) | 南満医学堂生物学教授。結婚 |
| 1915年(大正 4年) | 渡米、コロンビア大学 植物専攻科入学 |
| 1920年(大正 9年) | コロンビア大学で博士号を取得 |
| 1921年(大正10年) | 北海道帝国大学植物学教授 |
| 1923年(大正12年) | 次男、晃誕生。 |
| 1927年(昭和 2年) | 大阪毎日新聞社に入社 |
| 1928年(昭和 3年) | 「学天則」を製作。 大礼記念博覧会に出品 |
| 1930年(昭和 5年) | 著書「大地のはらわた」がベストセラー |
| 1945年(昭和20年) | 大阪毎日新聞社を退職 |
| 1947年(昭和22年) | 豊中市市議会議員に当選、議長となる(1年で辞任) |
| 1956年(昭和31年) | 1月4日、豊中市にて逝去。享年72歳 |

図.西村真琴肖像写真