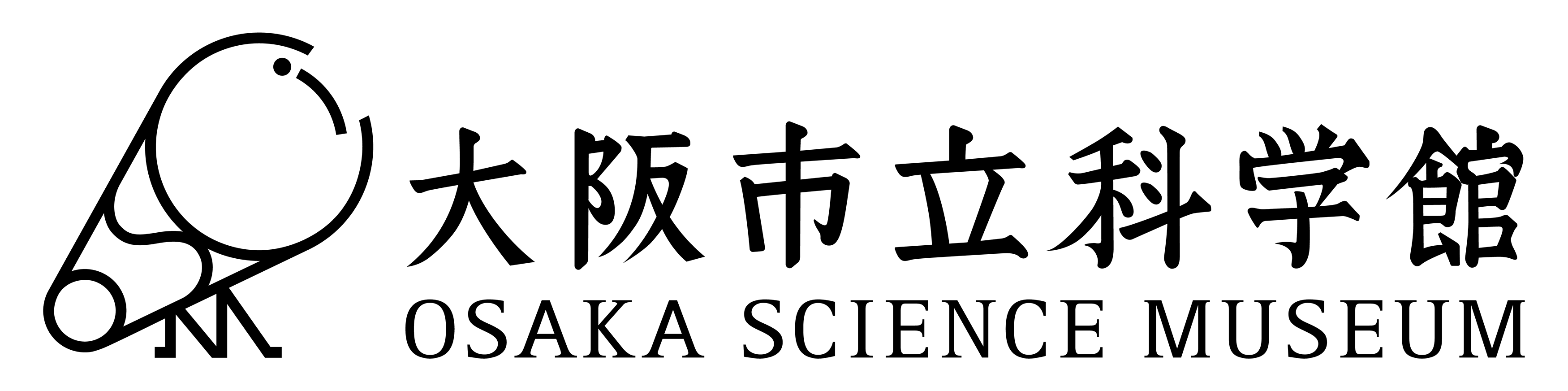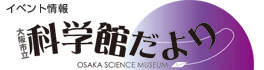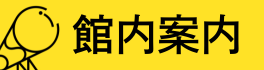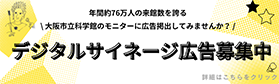スタッフだより
第117回 サイエンスショー「マイナス200℃のふしぎ」
2017年10月9日
今回のスタッフだよりは、サイエンスショー「マイナス200℃のふしぎ」の企画・制作を担当した大倉学芸員に話を聞きました。
液体窒素を使った実験ですね?

はい。サイエンスショーの冒頭で、冷たいものってどんなものを知ってますか?とこどもたちに聞くと、氷、アイスクリーム、ドライアイスという答えが返ってきますが、中には、液体窒素と答えてくれる子もいます。氷、アイスクリーム、ドライアイスは固体、つまり塊ですが、液体窒素は、空気を冷やして作る無色透明の液体で、温度は約マイナス200℃です。
デュワー瓶という魔法瓶の親戚のような容器に入れて保存しているのですが、そこからガラス容器に取り出すと液体はごぼごぼと泡立って、湯気のような白い煙が出ます。まるでお湯が沸騰しているようですが、冷たいのです。お湯の場合、湯気は水蒸気が空中で冷えてできた小さな水滴ですが、今のこの白い煙は、空気中の水蒸気が冷やされてできたもの、水滴ではなくおそらく小さな氷晶です。
どんな実験が見られるのですか?
まず、カーネーションを液体窒素の中で冷やしたらどうなるか見てもらいます。花びらの中の水分はあっという間に凍ってしまいます。触ると繊細なガラス細工のようにパリパリと崩れていきます。では、水分のないゴムボールはどうなるでしょう?ゴム風船では?カーネーションの時には見られなかった不思議な現象をご覧いただきます。
他にどんな実験が見られるのですか?

透明な傘袋を空気で膨らませ、それを液体窒素で冷やすとどんどん縮んでいきます。そして、下の方に何か液体のようなものができています。これは空気が液化したものなのです。空気は冷やすと液体になります。空気の中の大部分は窒素ですが、液体窒素は空気中の窒素を液化したものだったのです。
笛付きヤカンの中に液体窒素を入れると笛が鳴ります。非常に冷たい温度で沸騰しているのです。しばらくするとヤカンは凍り付きますが、よく観察すると不思議なことが起こっています。どんなことが起こっているのかは、見てのお楽しみ。
実験の途中、黒いものを冷やしていましたが?

はい。割れやすいものなのでアルミホイルで包んで保護していますが、中身は黒い色をした特殊なセラミクス、焼き固めたものです。超伝導体といいます。常温では磁石に反応しませんでしたが、冷えた今、磁石を近づけるとどうなるでしょう?N極を近づけても、S極を近づけても反発します。ちょうど鉄とは逆に磁石を嫌っていますね。磁石に近づけた時のこのような性質を鉄の強磁性に対して反強磁性と呼びます。実は電気と磁石には密接な関係があります。超伝導状態とは、電気抵抗がゼロになる、つまりいくらでも電流を流せるということなのですが、本日は、超伝導体の電気の効果ではなく、磁気的な効果をご覧いただこうという訳です。
金属に磁石を近づけると電磁誘導といって、金属に電流が流れます。そして同時に電流により磁石の接近を妨げる、つまり反発する力が生じるのです。ところがこの誘導電流は金属の持つ電気抵抗のため流れ続けることはありません。そのため、反発力が持続することはないのです。ところが、超伝導体は電気抵抗がゼロなのですから、反発力は消えません。このような超伝導体が磁石を斥けるような現象を発見者の名前をとってマイスナー効果とよびます。
では、まだ超伝導になっていない超伝導体のそばに磁石を置いて冷やしていったらどうなるでしょう?こんどは、俗にピン止め効果と呼ばれる現象を見ていただきます。冷えて超伝導になれば、マイスナー効果で磁石が跳ね飛ぶだろうと考えた方はスルドイです。しかし、やってみると磁石は跳ね飛びません。写真では超伝導体の上で磁石が浮き上がっていますが、ショーではさらに不思議な現象をご覧いただきます。何が起こるかは、見てのお楽しみ。
最後にひとこと

大倉 宏学芸員
冒頭、デュワー瓶からガラス容器に液体窒素を移した時、液体窒素がごぼごぼと沸騰しているのを見ていただきました。液体窒素の沸点はマイナス196℃。沸騰しているのですから、この状態での温度はマイナス196℃に違いありません。ところが沸騰が収まり、静かな状態になったとき温度を測ってみるとマイナス199℃です。温度が下がった?なぜ?
デュワー瓶という保存容器は、魔法瓶のようなものだと書きました。お湯を魔法瓶の中に入れておくと次第に冷めていきます。つまり、室温に近づいていくという訳。では、デュワー瓶に入れた液体窒素も室温に近づいていくのでしょうか。
たしかに、時間が経つと液体窒素は蒸発し、入れた量はだんだんと減って行きます。ところが、全て蒸発しない限り、デュワー瓶から取り出すと常に冷たいのです。そして容器から取り出した瞬間、上に書いたように沸騰してしまうのですが、しばらくすると温度は「自動的に下がり」マイナス200℃くらいになるのです。不思議です。
なぜ、デュワー瓶の中で液体窒素の温度は上がらないのでしょうか?なぜ取り出した瞬間より温度が下がってしまうのでしょうか?理由は皆さんで考えてください。
スタッフだより
- 第150回 ノーベル賞受賞100年記念「アインシュタイン展」
- 第149回 全天周映像作品「ブラックホールを見た日~人類100年の挑戦~」
- 第148回 プラネタリウム「天王星発見240年」
- 第147回 南部陽一郎生誕100周年記念 企画展示「ほがらかに」―南部陽一郎の人生と研究―
- 第146回 プラネタリウム「冬の天の川」
- 第145回 プラネタリウム「HAYABUSA2 ~REBORN」
- 第144回 サイエンスショー「ふしぎな形」
- 第143回 プラネタリウム「火星ふたたび接近中!」
- 第142回 ミニ企画「積み木のルーツ~フレーベル『恩物』」展
- 第141回 プラネタリウム「夜空の宝石箱『すばる』」
- 第140回 いろいろな楽器のグループ分け
- 第139回 サイエンスショー「電池がわかる」
- 第138回 プラネタリウム「星空歴史秘話」
- 第137回 プラネタリウム「木星と土星の世界」
- 第136回 「蜃気楼(しんきろう)」を見てみませんか?
- 第135回 プラネタリウム「宇宙ヒストリア~138億年、原子の旅~」
- 第134回 プラネタリウム。リニューアルの舞台裏
- 第133回 展示場のリニューアル
- 第132回 大阪市立科学館と大阪大学
- 第131回 展示場リニューアル準備 ~気象コーナー~
- 第130回「はやぶさ2」
- 第129回 スペシャルナイト「さよならインフィニウムL-OSAKA」
- 第128回「2018サイエンスサーカス・ツアー・ジャパン」
- 第127回「スーパー磁石で大実験」
- 第126回「科学デモンストレーター10周年」
- 第125回「火星大接近」
- 第124回 サイエンスショー「ふわふわ、きらきら!シャボン玉サイエンス」
- 第123回 プラネタリウム「眠れなくなる宇宙のはなし」
- 第122回 プラネタリウム「はるかなる大マゼラン雲」
- 第121回 サイエンスショー「虹でじっけん、光のせかい」
- 第120回 幼児のための企画展「にじのせかい」
- 第119回 プラネタリウム「ブラックホール合体!重力波」
- 第118回 企画展「大阪市立科学館資料で見るノーベル賞展」
- 第117回 サイエンスショー「マイナス200℃のふしぎ」
- 第116回 プラネタリウム「秋の夜長に月見れば」
- 第115回 「大人も子どもも、紫キャベツ!」
- 第114回 「空を眺めると…~夏の雲はモクモク雲~」
- 第113回 プラネタリウム「木星と土星を見よう」
- 第112回 プラネタリウム「見上げよう!未来の星空」
- 第111回 企画展「石は地球のワンダー~鉱物と化石に魅せられた2人のコレクション~」
- 第110回 プラネタリウム「見えない宇宙のミステリー~謎の光・X線をとらえろ~」
- 第109回 「星図の描き方」
- 第108回 サイエンスショー「静電気なんてこわくない!?」
- 第107回 プラネタリウム解説デビュー裏話
- 第106回 サイエンスショー「ふしぎな形にだまされるな!」
- 第105回 「化学と宮沢賢治」
- 第104回 プラネタリウム「星空オールナイト」
- 第103回 プラネタリウム「火星・土星・冥王星ツアー」
- 第102回 プラネタリウム「ファミリータイム」
- 第101回 この夏は「花火×化学」
- 第100回 プラネタリウム「銀河の世界」
- 第99回 プラネタリウム「星の誕生」
- 第98回 「スーパー磁石で大冒険」
- 第97回 「鉱物の結晶構造」
- 第96回 「だれでもできる!天体写真を写してみよう」
- 第95回 プラネタリウム「ロゼッタ、彗星を探査せよ」
- 第94回 サイエンスショー「フシギな偏光板」
- 第93回 企画展「光とあかり」
- 第92回プラネタリウム「ブラックホール」
- 第91回サイエンスショー「赤青緑の光サイエンス」
- 第90回国際光年協賛「花火の色とひかり展」
- 第89回プラネタリウム「天の川をさぐる」
- 第88回プラネタリウム「ボイジャー太陽系脱出」
- 第87回サイエンスショー「飛ばしてみよう!」
- 第86回 プラネタリウム「オーロラ」
- 第85回 サイエンスショー「バランス大実験」
- 新年のごあいさつ
- 第84回 プラネタリウム「ビッグバン~宇宙ヒストリア~」
- 第83回 サイエンスショー「水の科学」:凍らない水
- 第82回 プラネタリウム「宇宙人をさがす冴えたやり方―沈黙のフライバイ」
- 第81回 「はやぶさ2」 プラネタリウム&企画展について
- 第80回 サイエンスショー「空気パワー」
- 第79回 プラネタリウム「天の川って、なんだろう」
- 第78回 プラネタリウム「月へいこう!~おためし月面生活~」
- 第77回 オーストラリア・パワーハウスミュージアム訪問記(後編)
- 第77回 オーストラリア・パワーハウスミュージアム訪問記(前編)
- 第76回 プラネタリウム「南十字星にあいにいこう」
- 第75回 「都会の星」写真展
- 新年のごあいさつ
- 第74回 サイエンスショー「炎のアツい科学」
- 第73回 プラネタリウム「オーロラ」
- 第72回 企画展「色の彩えんす」まもなく終了
- 第71回 プラネタリウム「宇宙のトップスター」
- 第70回 国際会議で発表
- 第69回 サイエンスショー「マイナス200℃の世界」のご紹介
- 第68回 プラネタリウム2013年夏のプログラム紹介
- 第67回 くうきフシギ発見!~シーオーツーのひみつ~
- 第66回 プラネタリウム「未来の星座を見てみよう」
- 第65回 パンスターズ彗星!
- 第64回 サイエンスショー「サウンド・オブ・サイエンス♪」
- 第63回 『宇宙のハーモニー ~奇跡の地球に生まれて~』 のできるまで
- 第62回 プラネタリウム新プログラム「オーロラ」
- 第62回 プラネタリウム新プログラム「木星」
- 第61回 展示場3階「色の化学」
- 第60回 宇宙に浮かぶ望遠鏡
- 第59回 光のヒ・ミ・ツ
- 第58回 企画展「渋川春海と江戸時代の天文学」を開催します
- 第57回 新スタッフ紹介
- 第56回 プラネタリウム・キッズタイムと新プログラム
- 第55回 金環日食
- 第54回 そらみたことか-気象光学現象について-
- 第53回 電気科学館の思い出
- 第52回 科学デモンストレーターとは何か?
- 第51回 「世界化学年2011」を振り返る
- 第50回 プラネタリウムリニューアルオープン
- 第49回 皆既月食
- 第48回 新展示「風車」登場!
- 第47回 アンドロメダ銀河の正体
- 第46回 花火の化学展
- 第45回 七夕にまつわる新発見!
- 第44回 「蜃気楼」ってなんだろう
- 第43回 新館長よりご挨拶
- 第42回 科学館ミニブック 第2弾!第3弾!登場
- 第41回 世界化学年2011
- 第40回 アジアの星と神話
- 第39回 科学館のおすすめ展示 その2
- 第38回 はやぶさ帰還カプセル展示を終えて
- 第37回 科学館のおすすめ展示 その1
- 第36回 新スタッフ紹介
- 第35回 大型映像を見よう
- 第34回 「はやぶさ」遂に地球へ帰還
- 第33回 科学館もおでかけします
- 第32回 展示場をより楽しむ方法
- 第31回 サイエンスショーができるまで
- 第30回 科学館天文台
- 第29回 モバイルプラネタリウム
- 第28回 宇宙の「謎」を解き明かす
- 第27回 流星群を観察してみませんか?
- 第26回 20周年を迎えて
- 第25回 はじめまして!
- 第24回 「皆既日食」見て来ました!
- 第23回 「7月22日、日食を見よう!」
- 第22回 「広報担当S&Yの試写レポート」
- 第21回 「宇宙がわかる」
- 第20回 「HAYABUSA」公開開始!
- 第19回 「いろいろ集めてます!第2弾」
- 第18回 「世界天文年2009」
- 第17回 「元素がわかる」
- 第16回 「ペルセウス座流星群を見よう!」
- 第15回 「新!展示場 誕生」
- 第14回 「天の川を見よう」
- 第13回 「リニューアルまであと2ヶ月!」
- 第12回 「サイエンスガイドって?」
- 第11回 「137億年の歴史」
- 第10回 「プラネタリウムのライブ解説」
- 第9回 「いろいろ集めてます」
- 第8回 「電気びりびり」
- 第7回 「プラスチック 100年」
- 第6回 「プラネタリウムの今昔」
- 第5回 「結晶の世界」
- 第4回 「密着!学芸員」
- 第3回 「そらみたことか」
- 第2回 「流れ星を追いかける男」
- 第1回 「ほないくで」
開館日カレンダー
■は休館日です
本日のプラネタリウム
残席情報
本日は9:30開館です。
残席表示も9:30からご覧いただけます。
- 所要時間
- 約45分間
お客様の安全のため、途中入場できません。
ブラウザを更新してご確認ください